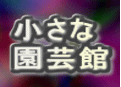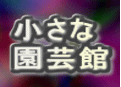|
真夏の暑い時期に、オレンジ色の大きく派手な花を次々と咲かせていく南国を感じさせる花。
頑強な性質で育てやすく、庭木として好まれている。 |
| ※ |
原産地は中国。 |
| ※ |
古くからあるノウゼンカズラの他にもいくつかの品種がある。 |
|
|
| 開花時期 |
| 【7月 ~ 9月中旬】 |
|
| ノウゼンカズラの欠点 |
|
| ☆ |
花に香りがないこと。 |
| ☆ |
花が短命で落ちやすいこと。 |
|
落下した花びらが変色などして、地面がきたなく感じられる。 |
|
|
|
| 名 前 |
ノウゼンカズラ 〔凌霄花〕 |
| 別 名 |
ノウショウカズラ 〔乃宇世宇加都良〕 |
| 英 名 |
Chinese trumpet vine |
| 類 別 |
ノウゼンカズラ科 [Bignoniaceae]
ノウゼンカズラ属 [Campsis] |
| 学 名 |
Campsis grandiflora |
| 性 質 |
落葉性 蔓性木本 |
| 原産地 |
中国、 北米(東南部) |
| 用 途 |
庭植え |
| 花言葉 |
「栄光」 |
|
| ◇ |
中国では山中に野生し、古くから薬として使われていた。
日本には平安時代の9世紀頃に渡来する。 |
| ◇ |
ポール仕立て、アーチ、フェンスなどに向く。 |
| ※ |
1つの花は2~3日しか咲いていない。 |
| ※ |
勢力旺盛で成長が激しく、つるとなって伸びた新しい枝の先端に花芽を作るので、小さく育てる鉢植えは難しい。 |
|
|
|
|
| 花の特徴 |
花の形はラッパ型で、花の先が5片に裂けている。
花の大きさは6cm~7cmほどで、茎の先にまとまって横向きに咲く。
通常は花序が垂れ下がるので、ポール仕立てやフェンス仕立てなどが適している。 |
|
|
花色は、オレンジ色が多いが、より赤色がかったのや黄色い花色もある。
雄しべは4本で、そのうち2本が長い。
雌しべは先が舌状に広がって2つに分かれている。 |
|
|
|
| 木の特徴 |
成長が早く、1年でつるが数mは伸びる。
つるの途中からから根を出し固着するすることができる。
幹は太くなり、年月がたつと、木の様になる。
ささえがないと横にはっていくが、ささえがあれば5mほどの高さには成長する。 |
| 結実しにくい |
| 日本で栽培しても、結実しにくいとされる。 |
| ※ |
花粉の媒介するものが日本にはいない為と考えられている。 |
|
|
|
| 薬用利用 |
| 中国では薬用利用されている。 |
| ※ |
花を干したものは、利尿などに効力がある。 |
|
→ 日本では有毒植物と考えられている。 |
|
|
|
| ノウゼンカズラ 〔凌霄花〕 - 和名 |
| 諸説あるが、平古くは「ノウショウ」と呼び、『本草和名』(ホンゾウワミョウ)(日本最古の本草辞典)にノウショウカズラ〔乃宇世宇加都良〕と表記されていたことによるといわれる。 |
|
|
|
|
| Campsis grandiflora - 学名 |
| 諸説ある。 |
| ◇ |
Campsis(カンプシス) : ノウゼンカズラ属
→ ギリシャ語の「Kampsis」(湾曲、曲がっている)が語源。 |
|
おしべの形が曲がっていることによる。 |
| ◇ |
Grandiflora : 大きい花の |
|
|
|
ノウゼンカズラ属は、ほとんどが「ノウゼンカズラ」と「アメリカノウゼンカズラ」と、それらの雑種からなる。
日本で一番よく見られるのは「ノウゼンカズラ」。 |
|
|
| アメリカノウゼンカズラ 〔亜米利加凌霄花〕 |
北米のフロリダ、テキサスからペンシルバニアにかけて野生する。
野生状態では、雑木となり他の木を圧倒していくほどたくましい。
花色は、ノウゼンカズラよりも落ち着いた色合いの赤みがかったオレンジ色が多いが、黄色もある。
花の筒が、ノウゼンカズラより細長く、直径が狭い。 |
|
| 英 名 |
Trumpet vine、 Trumpet tree |
|
|
|
|
 |
|
|
アメリカノウゼンカズラ |
|
|
| 別 名 |
コノウゼン |
| 学 名 |
Campsis radicans |
| 原産地 |
北アメリカ (南東部) |
|
| マダム・カレン |
ノウゼンカズラとアメリカノウゼンカズラとの雑種で、近年、欧州から輸入されて広まったもの。
花形はノウゼンカズラとアメリカノウゼンカズラの特徴を合わせ持ち、花筒が短く、花径が広い。
花色は明るい朱紅色で、黄色い品種もある。
花は比較的落ちにくい。 |
|
|
| タカラヅカ・ゴールド |
明るい黄色い花を咲かせる。
花持ちがよい。 |
|
|
| コンテッサ サラ |
薄いピンク色の花を咲かせる。
常緑樹であるが、耐寒性がないので、地植えは難しい。 |
|
|
|
|